貴金属の活用+オープンイノベーションで日本の半導体技術に革新を
- 採択テーマ
- 貴金属配線による裏面電源供給ネットワークの形成
- 受賞
- 2021年度 ゴールド賞受賞
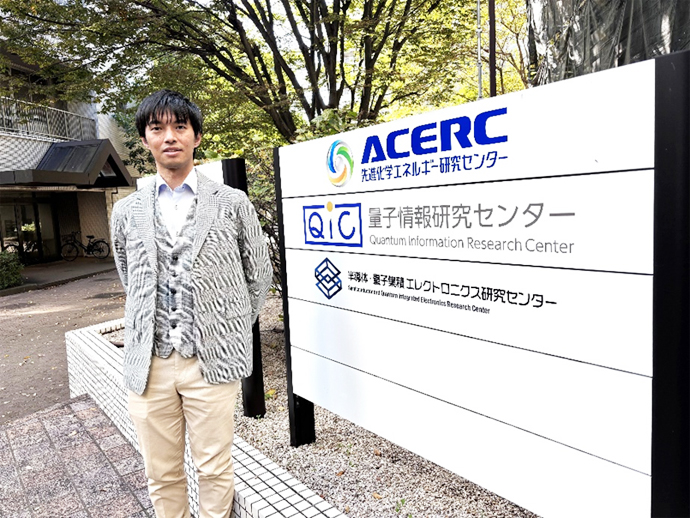
田中貴金属記念財団では貴金属の新分野を開拓・醸成し学術、技術と社会経済の発展に寄与することを目的に、貴金属が貢献できる新しい技術や研究・開発を行う団体を表彰、助成金を授与しています。今回は貴金属を活用した配線ネットワークの最適化で半導体の低省電力化に取り組み、2021年ゴールド賞(助成金200万円)を受賞した横浜国立大学大学院の井上史大准教授に研究の概要や今後の目標についてお話を伺いました。
「チップレット」で半導体の低省電力化に挑む
まずは、先生の来歴と研究室の概要を教えてください。

私は国内の大学院で博士号を取得後、2011年から約10年間、ベルギーにある世界最大の半導体研究開発コンソーシアムimec(Interuniversity Microelectronics Centre)で半導体の後工程に関する研究に従事しました。2021年4月からは横浜国立大学大学院に拠点を移して研究を続けています。研究室には現在15名の学生が在籍しており、主にチップレットという半導体最新技術の研究に取り組んでいます。
チップレットとは、どのような技術で、なぜ必要とされているのですか?
近年、自動運転、遠隔医療診断や生成AIなどの技術進展によるデータ処理量が爆発的に増え続けており、その処理のための「データセンター」の需要が急拡大を続けています。経済安全保障上からも重要度が増しているデータセンターですが、莫大な量のデータを処理するために多大な電力を消費することが、大きな課題となっています。データセンターにおける電力消費量の約80%は半導体デバイスによるもの。したがって半導体をいかに低消費電力化するかが、大きな課題となっています。
この課題解決に大きな役割を果たすと期待されている集積技術が「チップレット」です。チップレットとは、小さな独立したチップ(集積回路)を複数組み合わせて、一つの大きな機能を持つシステムを作る技術のこと。つまり、1枚のチップにすべての機能を作り込むのではなく、個々の機能ごとに小さなチップを作り、目的に応じて複数のチップを組み合わせ、基板上の配線でつなげる技術です。この配線を最適化することでエネルギー効率を上げ、省電力化が実現できると考えられています。さらに、必要に応じてチップを選んで組み合わせることができるので少量多品種で半導体を製造できる、良品選別をして全体の性能向上を図りやすい等のメリットもあります。今回、ゴールド賞をいただいた「貴金属配線による裏面電源供給ネットワークの形成」ではチップレットで各チップをつなぐ「配線」に着目しており、最終的には半導体の低省電力化を目指しています。
銅より信頼性の高い「ルテニウム」配線の実用化を目指して
ゴールド賞を受賞した研究「貴金属配線による裏面電源供給ネットワークの形成」の概要を教えてください。

従来、半導体では配線に主に「銅」が使われてきました。銅は非常に抵抗が低く配線材料として優れていますが、小さくなればなるほど信頼性(耐久性)が低くなり、壊れやすくなるという弱点があります。一方、半導体の配線は年々小さくなり、今や10ナノ近くにまでなっていますから、銅の信頼性についての懸念が大きくなってきたわけです。そこで、銅に代わる材料として注目を集めているのが、ルテニウムです。ルテニウムは非常に融点が高く、銅に比べて非常に信頼性の高い(破損しづらい)配線を作ることができます。もちろん、銅よりもルテニウムのほうが希少で高価ですが、ルテニウムは配線をより小さくしても信頼性を担保できるため、全体的な使用量は銅に比べてかなり少なく抑えられると考えられます。
さらに、半導体の配線に関しては素材だけではなく、その構造についても今、非常に大きな変革が起きています。これまで配線はチップの表面にだけ作られていたのですが、近年、表面だけでなく裏面にも配線を付けようという試みが本格化しているのです。今回の「ゴールド賞」は、①貴金属(ルテニウム)の活用と②裏面配線の2つのアプローチで新しい配線ネットワークの構築を目指している点を、高く評価していただいたものと自負しています。
ルテニウムを半導体配線に活用する技術はあまりに難易度が高いため、ルテニウム配線構造を作る技術を確立しているのはimecなど一部の研究機関やグローバル企業のごく一部に限られており、まだ実用化には至っていません。日本でも、国の補助を受けて研究者チームが一丸となって研究を進め、ようやくルテニウム配線構造を作って、配線の信頼性を評価するフェーズまでやってきました。現在、当研究室をはじめ国内各地の研究機関が基礎データの計測・収集・分析を重ねており、いよいよルテニウム配線の実用化に向けたフェーズに入ったところです。当研究室でもルテニウムをはじめ貴金属の活用に幅広い知見をお持ちの田中貴金属さんに引き続きサポートやアドバイスをいただきながら、より効率的で環境負荷の少ない配線ネットワークの構築実現を目指して、研究に取り組んでまいります。
競争ではなく連携を。オープンイノベーションで半導体の未来を切り拓く
研究と同時に、人材の育成やネットワーキングにも力を入れています。どのような想いがありますか?
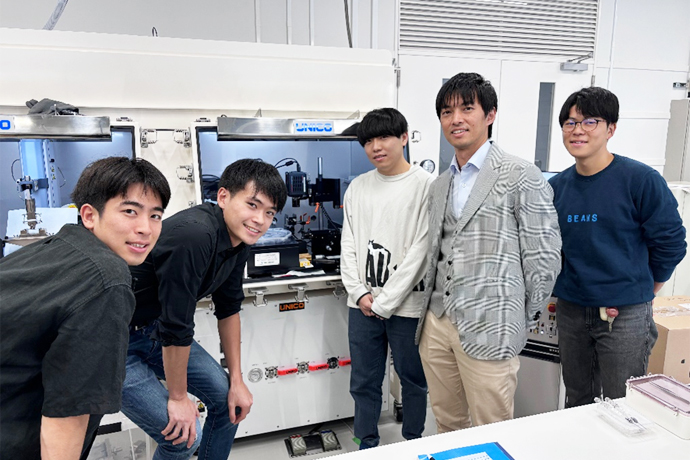
国や研究機関、企業が垣根を越えて参画する半導体エコシステム、日本版imecのような組織を作り、半導体産業における日本のプレセンスを再び高めていきたいと考えています。1980年代ごろまで半導体は日本のお家芸と言える分野で世界シェアの約50%を占めていましたが、今や世界の半導体市場における日本のシェアは10%以下まで落ち込み、日本のプレセンスは低下しています。
一方、海外に目を向けると、一社単独では困難・不可能な研究開発はimecのようなオープンイノベーション拠点で行われるようになっています。imecは非営利機関ではありますが、年間1300億円を超える収益があり、その約8割は企業が拠出する研究費です。国ではなく企業が主体となることによって、最先端の情報や技術が集まり、本当に市場が求める実用的な技術を研究できる点が魅力で、世界中の企業や研究機関から優秀な研究者が集まっています。
日本でも企業が技術開発を競うのではなく、技術を持ち寄ってエコシステム全体で研究開発から最先端半導体の国産化を見据えて協力するオープンイノベーションな組織を作ることで、大きなイノベーションを起こすことができるはずです。現在、私が代表を務めるコンソーシアム「3DHI」は、これを実現するために立ち上げられたもので、日本版imecのような存在を目指して、最先端半導体のコア技術の一つである3D集積技術をテーマに産学が連携して研究を進めるとともに、半導体人材育成に取り組んでいます。
あらゆる立場のプレイヤーがつながる半導体エコシステム 日本版「imec」の構築を目指す
半導体産業発展のためには、どのような人材育成が必要でしょうか?また、先生ご自身はどのような役割を果たしたいと考えていますか?
これまでのような「特定分野の専門家」だけでなく、「幅広い領域に知見のある人材」が求められるようになっていると実感しています。というのも、先ほどから申し上げてきたとおり、最先端半導体の開発・製造には極めて広範かつ難易度の高い技術が必要であり、企業や研究機関、国や自治体など多くのプレイヤーとの連携が欠かせないからです。そこで、専門人材の育成と人材の連携を目指す取り組みの一環として、2024年4月に横浜国立大学内に半導体・量子エレクトロニクスセンターを設立しました。今後は自身も一研究者としてチップレットや3D集積の研究に取り組むと同時に、当コンソーシアムや「3DHI」の活動を通じて、半導体に関わる多彩なプレイヤーを「つなぐ」役割を果たし、次世代の半導体産業の発展をけん引する次世代のエコシステムを構築していきたいと考えています。半導体産業が衰退して久しいと言われる日本にも、特に半導体製造装置や材料の領域では高い技術があり、優れた企業や研究者も多数存在しています。これらのポテンシャルを存分に生かして半導体業界における日本のプレセンスの復活に貢献できるよう挑戦を続けてまいります。

Profile
井上 史大(いのうえ・ふみひろ)
横浜国立大学大学院工学研究院 システムの創成部門 准教授 博士(工学)
1986年、関西大学大学院で博士号を取得後、2011年から世界最大の半導体研究開発コンソーシアムimec(Interuniversity Microelectronics Centre)で主に半導体後工程の研究に従事。2022年日本人初のIEEE EPS国際賞受賞。2021年4月横浜国立大学准教授。2022年に70社以上が参画する半導体コンソーシアム3DHIを設立。「つなぐ」をキーワードに半導体分野の産学連携に精力的に取り組む。
